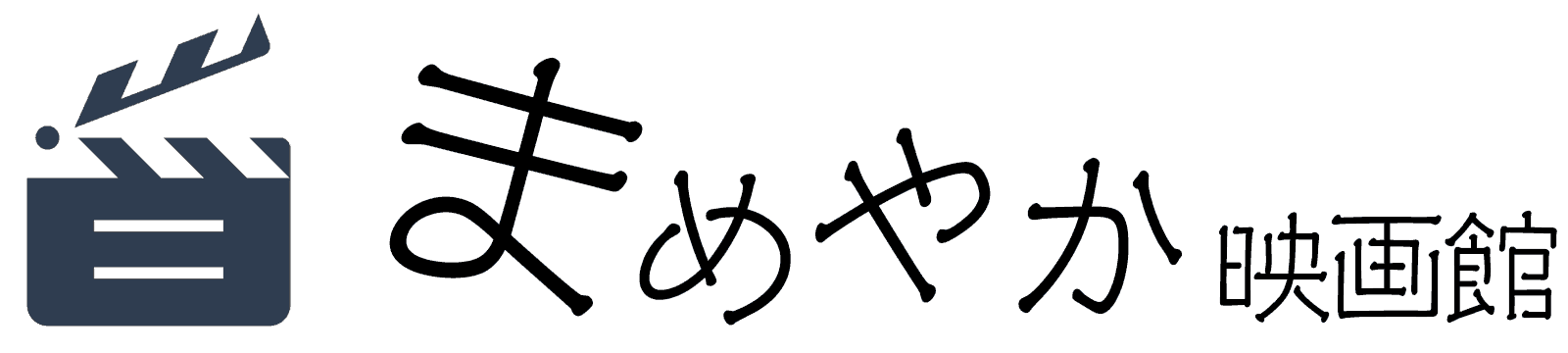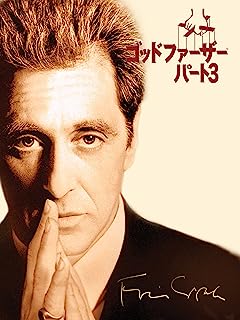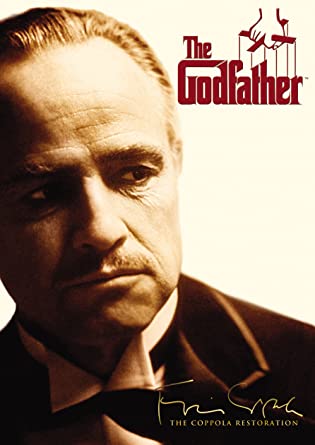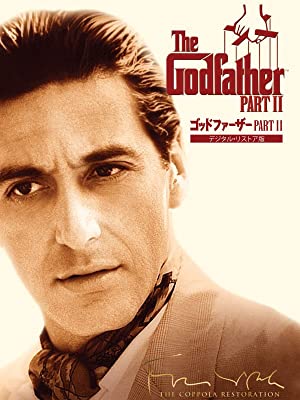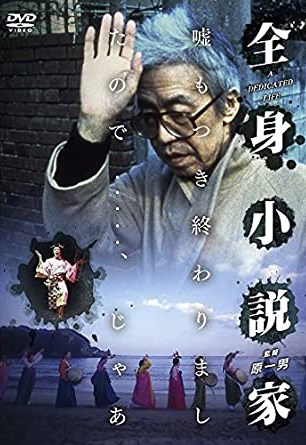
『全身小説家』(1994年)
主演:井上光晴
1994年度キネマ旬報日本映画ベストテン第1位、第49回毎日映画コンクール日本映画大賞受賞。作家・井上光晴の晩年の活動の様子や、彼を取り巻く人々のインタビューを通して、ひとりの作家の「虚」と「実」を克明にとどめていく。井上と親交があった、埴谷雄高氏や瀬戸内寂聴氏も出演。異色ドキュメンタリー作品の感想。
『全身小説家』一筆感想

ドキュメンタリーの内容
小説『書かれざる一章』『ガダルカナル戦詩集』などで知られる作家・井上光晴がガンで逝去するまでの数年間に密着したドキュメンタリー作品。井上が全国13か所で開催している文学伝習所での受講生たちとの交流や、講演会の様子、文学仲間の証言をおさめて、井上の人間性に迫っていく。映画の後半、関係者の証言を通して、井上光晴のキャリアに「虚構」があることが判明する。
『全身小説家』レビュー
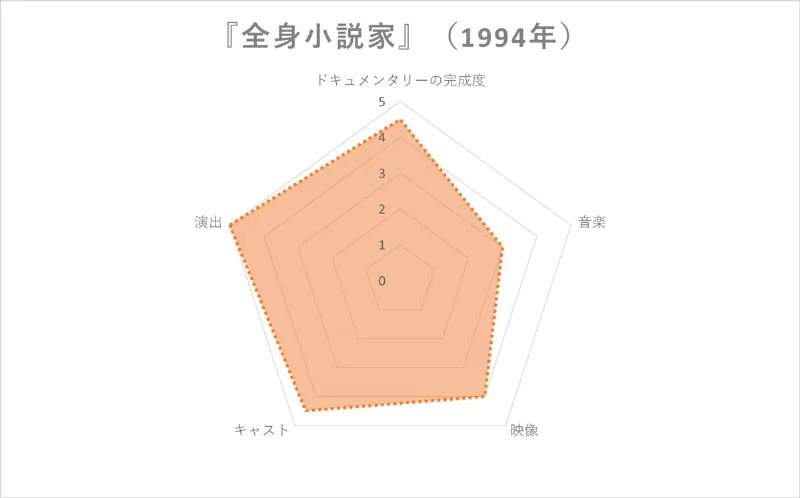
作家・井上光晴の晩年を追い続けた長編ドキュメンタリー
井上光晴の小説を読んだことがないまま、この映画を見てしまいました。原一男監督による前作のドキュメンタリー映画『ゆきゆきて、神軍』が衝撃的だったため、今作もいかにも一筋縄ではいかない人物が登場するのだろうなぁ……と期待値が上がったのです。
で、期待値を超えたかと言いますと、正直微妙です。
つまらないというわけではありません。なんとも言えない余韻を残す映画だなと。はからずも、ひとりの作家の深淵をのぞきこんだような気分といえばいいでしょうか。
原一男監督は、作家・井上光晴のエネルギッシュな活動を追いながら、がんとの戦いを描いていきます。井上は1989年にS字結腸がんを発症後、手術を受けるるものの、しばらくして肝臓に転移したため、2度めの手術を受けました。手術シーンは「そんなところまで見せてもいいのか」とのけぞってしまうほど踏み込んだ撮影をしています。(苦手な人は、視聴をお控えください)
闘病を続けながらも、井上の活動はいよいよ精力的になっていくようでした。どこか ふてぶてしさすら感じる井上の言動は、理屈抜きに聞く者の魂を揺さぶるような迫真力と説得力に満ちあふれています。
もし井上が1992年にがんで死去しなければ、『全身小説家』は10年にわたっての撮影を考えていたとのこと。それくらい原一男は、この井上光晴という人間に深みを感じていたのでしょう。結局、『全身小説家』の撮影は3年間で終わり、編集作業等で2年を費やして、1994年に公開されました。
文学伝習所のお弟子さんたちの艶っぽさ
カメラは井上光晴が開催した文学伝習所での講義風景や受講生たちとの交流の様子をいきいきと活写しています。特筆すべきは、女性のお弟子さんたちのインタビューです。それは師匠に対する「傾倒」「心酔」というレベルを超越して、「女」として井上を深く慕っている様子が映し出されています。
彼女たちはそれほど若くはありませんが、井上を語るときの身振りと口ぶりに、なんともいえない華やぎと艶が感じられるのです。ある女性は、インタビューで「永遠に心の中の夫」というきわめて強い言葉をもらしているほど。率直に言って、僕たち観客から見たら、明らかに異様なほどの思い入れです。それは「モテモテ作家とその取り巻き」といった牧歌的な関係ではなく、いささか危険な影響力の介在を示唆しています。
でも考えてみたら、井上は言葉のプロフェッショナルであり、世俗の基準とは軌を一にしない独特の感性と価値観の持ち主です。井上が放つ、ときにやさしくときに激越な言葉は、文学に救いを求めるある種の女性のデリケートな琴線に触れたのではないでしょうか。少なくとも、教え子である彼女たちにとって井上光晴とは、文学のメンターを超えて、彼女たちの「生」に輝きや潤いを与えた存在だったようです。
映画を見ていていささか気になったのは、出演していた井上の妻・郁子さんの存在でした。この映画を見て、彼女の胸中にはどんな気持ちが去来していたのでしょうか。
作家の人生の ”虚実” が明らかになっていく
映画の後半、井上自身が著した個人年譜や自叙伝に書かれている内容と、井上の関係者の証言内容に、けっして小さくはない齟齬が明らかになっていきます。井上自身が公表している経歴に「虚構」があるのです。
かつて若かりし頃の井上とともに左翼運動に身を投じた女性の発言によると、「すぐばれるうそ」とのこと。しかし、監督原一男は、井上を咎めることはしません。井上が想像力によって産み出した「虚構」の過去を、モノクロのドラマで再現し、ドキュメンタリーのなかに挿入しています。まさに『全身小説家』は、虚実入り乱れた映像作品の様相を呈してくるのです。
見る人によっては『全身小説家』を見て、井上光晴という作家にいかがわしさを感じるかもしれません。しかし彼は筆舌に尽くしがたい戦中・戦後の時代を生き抜き、言葉と物語の力でたくましく身を立ててきた人です。虚構の力で自分の空虚な部分を埋め合わせ、整合性を図らないと、井上の人間存在は根底から瓦解していたのではないでしょうか。
井上光晴は、全身全霊で「虚構」を生きるというしかたで ”現実の生の手応え” をつかんでいたのかもしれません。表面的な善悪はどうあれ、それはひとつの尊重さるべき生き方ではないかと。
『全身小説家』のキャストについて
井上光晴
これまでの人生で多くの不条理を経験してきた人なのでしょうか、面立ちに、「一歩も引かないぞ」という気骨がうかがえます。情熱があり、ユーモアがあり、弁も立つ。自身が主催する文学伝習所のなかでは慕い仰がれる存在です。
きっと作家としての才能もあるのでしょう。しかしながら、『全身小説家』が映し出す井上光晴には、何か心を許せないものがあるのです。本人が書いた年譜や経歴に、事実と食い違う点があることがその理由ではありません。むしろ、本人自ら「嘘」を目立たせているようにさえ思えるふしがあります。そこにこの人の作家としての意気地(いきじ)と覚悟が感じられて、感服してしまいました。
僕が井上に対して違和感を禁じえないのは、妻である郁子さんに対する、彼の言葉遣いです。郁子さんに対する井上の言葉には、いつも、あるかなきかの微細な苛立ちのようなものが感じられます。そこにはパートナーへの敬意がいささか不足しているように思うのです。なぜだろう? そのことが喉の奥に刺さった小さな魚の骨のように、不快な感覚としてずっと残っています。
埴谷雄高
日本の文学史や思想史に疎い僕も、この人の名前は知っていました。「死霊」という形而上小説で有名です。この人が考える「宇宙」とは「無限」とは何だったのでしょう? 今の時代、ニーズの少ない領域ではありますが、どの時代にも「存在そのものの不可思議」に魅了される人々が一定数います。埴谷雄高の本はこれからも手に取られるでしょう。
『全身小説家』とは、埴谷雄高が考えた呼称です。井上光晴と親しく打ち解けて付き合っている様子が映し出されています。撮影当時、埴谷雄高は80歳くらい。年配の方によく見られる、首から上の不随意運動があるとはいえ、かくしゃくとしています。頭脳も明晰で、やはり作家だけあって適確な日本語を話す人だと感心しました。
井上について語る埴谷雄高のインタビューで強く印象に残っている言葉があります。
(井上光晴が女性を口説くことについて)3割バッター。10人くどいて3人なんですよ
こういうデリケートな内容をインタビューであけすけに話してしまうほど、埴谷雄高も井上光晴も世俗の基準とは大きくはずれた場所で生きているのだなとビックリしました。
瀬戸内寂聴
井上光晴の文学上の友人として出演。撮影当時、瀬戸内寂聴は古希に近い年齢ですが、童女のようにかわいらしい面立ちです。
1992年、井上の葬儀のシーンで、瀬戸内寂聴は弔辞のなかでこう述べています。
「性」抜きの稀有な男女の友情をまっとうする長い歳月を共有した
なぜわざわざ、こういう持って回った言い方をしたのかわかりません。でも、本人がそう言っているのだから、それでいいじゃないかと個人的には思います。
彼女もまた作家であり、「虚構」の持つ力を信じている人です。己の「業」を真摯に見つめ続けた生涯だったのではないでしょうか。この人もまた、まごうかたなき『全身小説家』だと僕は考えています。
『全身小説家』作品情報
| 監督 | 原一男 |
| 撮影 | 大津幸四郎 |
| 制作 | 小林佐智子 |
| 音楽 | 関口孝 |
| 出演 | ・井上光晴 ・井上郁子 ・埴谷雄高 ・瀬戸内寂聴 ・野間宏 ・文学伝習所の参加者 |
| 上映時間 | 147分 |
| ジャンル | ドキュメンタリー |

「ドキュメンタリー」という形を借りたフィクション
『全身小説家』という映画を見て、つくづく考えさせられたのは、ドキュメンタリーというものの本質です。監督・原一男は、井上光晴の経歴の虚構性に肉薄していきながらも、作家の「虚」と「実」をそのまま肯定しているように僕には思えました。撮影が進んでも、井上本人は弁明すらしていません。悪びれる様子もなく、バツの悪そうな表情さえしていないのには驚いてしまう。
そう、井上は一貫して、超然としているのです。
当たり前ですが、監督の手で選択的にカットされたシーンもたくさんあるでしょう。都合の悪いシーンや、整合性を欠くシーンは切り落とされているかもしれない。そう考えると、「ドキュメンタリー」という表現形式も、監督の意図が入り込むという意味で、「虚構」なのかもしれませんよね。
あなたは「ドキュメンタリー」と聞いてどういうイメージをお持ちでしょうか? 映画やテレビにおける「ドキュメンタリー」には、動かしがたい堅牢な現実が映し出されているという安心感がありませんか?
でも実際はどうなんでしょう?ドキュメンタリー「作品」としての体裁を整え流れをよくするために手が加えられていますよね。事実やデータに嘘はないとしても、何から何まで「ありのまま」というわけではないのです。そこには制作サイドの「観客にはこう見てほしい」という意図が入っています。つまり「作品」として提供された時点で、「ドキュメンタリーという形を借りたフィクション」になってしまうのではないかと。
ワイドショーやニュースもまた「虚構」の要素がゼロとはいえません。事実やデータにごまかしがなくても、情報の「伝え方」に印象操作がなくもない。それは悪いことではありません。ファクト(事実)を効果的にわかりやすく伝えるためにも、程度の差こそあれ「虚構」による助力は必要なのです。
そういう意識をもつと、日々メディアが発信する情報は「鵜呑み」にする対象ではなく、自分のアタマで考えるための判断材料として位置づけることができるでしょう。
思うに僕たちは、「虚構」に対してもっと寛容に鷹揚に構えてもいいのかもしれません。近年やたらとエビデンスいう言葉が飛び交っていますが、「エビデンス」という考え方それ自体にも「虚構性」が含まれると言ってしまうのは暴論でしょうか。
何もかも事実や証拠や裏付けや実証で塗り固めた社会というのは、なんとも嘘っぽいです。人間理解の貧しい社会といいましょうか。
この世界は「現実」と「虚構」が裏表になって、円滑に機能し回転しています。もしも「虚構」を取り除いてしまったら、人間の営為はままならなくなるのは火を見るより明らかです。
なんとなれば、人間は言葉による「虚構」を持つことによって、進歩を遂げてきたのですから。
『全身小説家』の動画をデジタル配信しているサービスは?
※ただし時期によっては『全身小説家』の配信およびレンタル期間が終了している可能性があります。