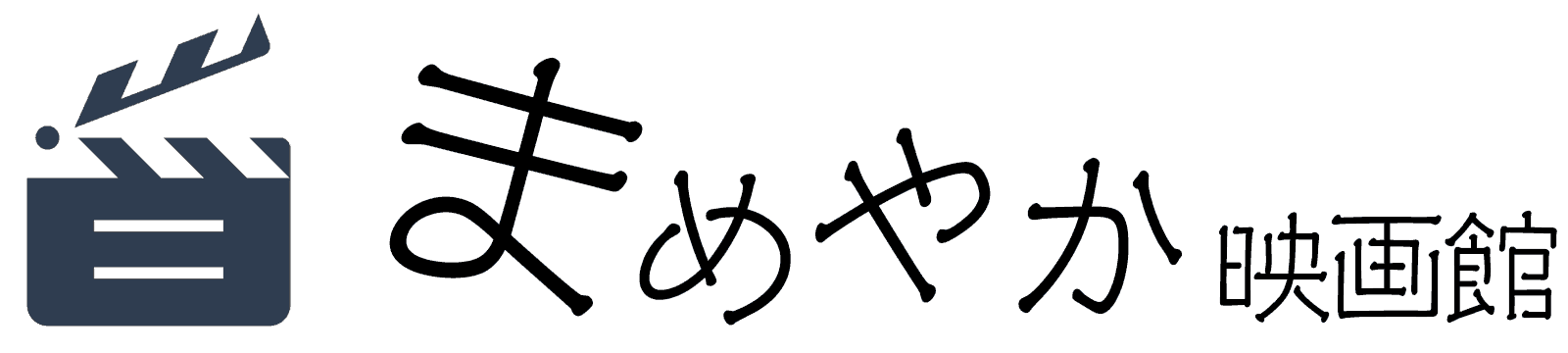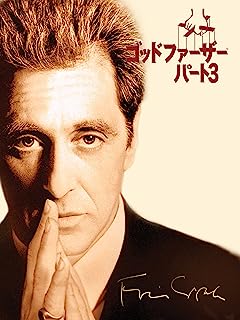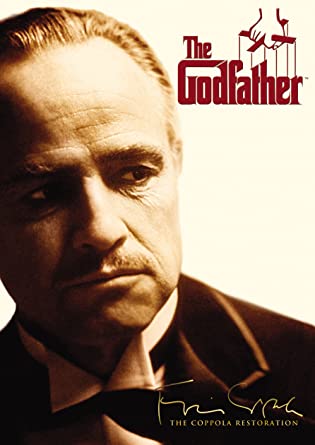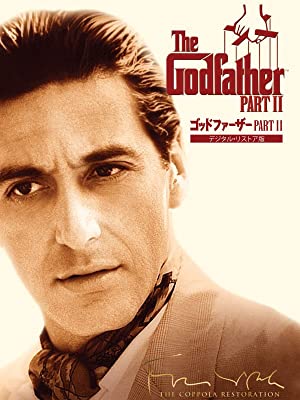『ベン・ハー』(1959年)
主演:チャールトン・ヘストン/スティーヴン・ボイド/ヒュー・グリフィス
原題:Ben-Hur
イエス・キリストが生きていた頃のローマ帝国にユダヤの王族として生まれたベン・ハーの数奇な人生を描いたスペクタクル叙事詩。途方もない制作費を投じて、70ミリの大画面で再現した戦車競走のシーンは圧巻。主人公の運命を通して、キリストの降誕と布教、処刑までを荘厳に描いた本作は、今もなお20世紀を代表する名作映画との呼び声が高い。名作映画『ベン・ハー』の感想と考察、ドラマの見どころや、登場人物のレビューを綴ります。
- 『ベン・ハー』の作品情報、あらすじが知りたい!
- なぜこの映画がスゴいのか教えてほしい!
- この映画の監督について知りたい!
- 作品の考察、解説、感想が読みたい!
- 出演者についての情報を知りたい!
『ベン・ハー』(1959年)作品情報
一筆感想

作品データ
| 監督 | ウィリアム・ワイラー |
| 助監督 | ガス・アゴスティ |
| 脚本 | カール・タンバーグ |
| 制作 | サム・ジンバリスト |
| 原作 | ルー・ウォレス |
| 撮影 | ロバート・L・サーティーズ |
| 音楽 | ミクロス・ローザ |
| 出演 | -チャールトン・ヘストン (ジュダ・ベン・ハー) -スティーヴン・ボイド (メッサラ) -ジャック・ホーキンス (クイントス・アリウス) -ハイヤ・ハラリート (エスター) -ヒュー・グリフィス (族長イルデリム) -マーサ・スコット (ミリアム) -キャシー・オドネル (ティルザ) -フィンレイ・カリー (バルタザール) |
| 上映時間 | 212分 |
| ジャンル | アクション/史劇 |
『ベン・ハー』あらすじ

約2000年前、エルサレムから南にあるベツレヘムの地で、イエス・キリストが誕生。
その頃、地中海東岸のユダヤの地は、初代皇帝アウグストゥスが治めるローマ帝国の属州だった。
支配国ローマの徴税に呻吟していたユダヤの民は、自分たちを解放してくれる救世主の現れることを待望していた。
26年後、ティベリウス帝に変わったローマは、エルサレムの地に新しい総督を派遣。
その総督の右腕である司令官としてメッサラが就任。
彼は、少年時代をこのエルサレムの地で過ごしていた。
そんなメッサラのもとに祝福に駆けつけたのが、幼馴染みのユダヤ王族の息子、ベン・ハーである。
ふたりは再会を喜ぶのも束の間、ローマとユダヤの乗り越えがたい確執はいかんともしがたく、反目し合ったまま分かれてしまう。
後日、新総督と司令官メッサラを筆頭にローマ軍の行進セレモニーの最中、事件が起こる。
ベンと妹ティルザがハー家の2階からセレモニーを見物していると、瓦が崩落。
下を通りかかった新総督に命中し落馬してしまう。
明らかに事故だが、ベンとその母、妹は反逆罪に問われてしまう。
メッサラに陳情するベン・ハーだが、司令官は幼馴染みの情状を酌量する余地は微塵もない。
ベンを裁判なしでガレー船へ送りこみ、その母と妹を地下牢に入れるのだった。
絶望したベン・ハーは冷酷なメッサラに復讐を誓う。
ガレー船へ送られる途中、ナザレの地で、ベン・ハーは渇きのために命の落としかける。
ちょうどそのとき、ローマ兵の制止をふりきって彼に一杯の水を差し出した人物がいた。
ベン・ハーは九死に一生を得るが、その人物がイエスその人であることを彼は知るはずがない。
それから3年 ━━
ベン・ハーはガレー船の船底で他の囚人たちと漕ぎ手として働き続けていた。
その眼光は鋭く、かつての品位に満ちた精悍さは失われて、野獣のごとき猛々しさをむき出しにしている。
メッサラへの復讐のためだけに露命を繋いでいるかのようだ。
海軍を統率指揮する執政官アリウスは、囚人の中でも毛色が違うベン・ハーの存在に強い関心を示した。
やがてローマ海軍は、マケドニアとの海戦を迎える。
アリウスばベン・ハーが乗る旗艦にマケドニア軍は船ごと突っ込み、兵士たちが闖入。
白兵戦を強いられ海に投げ出されたアリウスを、ベン・ハーは海に飛び込み救出。
筏の上から沈む旗艦を眺めながら絶望するアリウスだったが、実はローマ軍が勝利したことを知る。
ローマに戻ったアリウスとベン・ハーに待っていたのは、皇帝ティベリウスの祝福とローマ市民の歓呼の声だった。
アリウスは命の恩人であるベン・ハーを手厚くもてなすだけでなく、自分の養子に迎える。
養父の支援を受け、戦車競技者として功成り名を遂げたベン・ハーは郷里エルサレムに戻ることを決断。
途中、アラブの族長イルデリムと出会ったベン・ハーは意外な事実を聞かされる。
あのメッサラが戦車競争に出場するというのだ。
ベン・ハーの競技者としての腕を見込んで、戦車競争への出場を依頼するイルデリム。
だが母と妹の安否が気になる彼には競争に出場する余裕がない。
丁重に断り、エルサレムへの帰郷を急ぐ。
エルサレムに戻ったベン・ハーは、かつての執事の娘であり、最愛の人エスターと再会。
やがてエスターの口から、母と妹がすでに亡くなったと聞かされたベン・ハーは憤りと絶望を胸に秘め、族長イルデリムのもとに戻る。
戦車競走当日 ━━
会場で大観衆の声援を浴びているベン・ハーはイルデリム所有の白馬に引かせたチャリオットの御者としてエントリーしていた。エントリー9台のトリを飾るのが優勝常連のメッサラだ。
黒馬に引かせたギリシャ式チャリオットは一見豪勢だが不穏な輝きを放っていた。
因縁の二人は、今まさに火花を散らせて激突しようとしている。
観衆が固唾を呑む中、総督ピラトゥスが白布を落とすのを合図にレースがスタート。
この戦車競走、ただではすみそうにない。
『ベン・ハー』作品の解説

『ベン・ハー』の輝かしい実績~ハリウッドの金字塔にして、いまだレジェンド
本作は第32回アカデミー賞11部門でオスカーを受賞。
| 作品賞 | 『ベン・ハー』 |
| 監督賞 | ウィリアム・ワイラー |
| 主演男優賞 | チャールトン・ヘストン |
| 助演男優賞 | ヒュー・グリフィス |
| 美術賞 | ウィリアム・A・ホーニング/エドワード・C・カーファーニョ |
| 撮影賞 | ロバート・L・サーティース |
| 衣装デザイン賞 | エリザベス・ハフェンデン |
| 編集賞 | ジョン・D・ダニング/ラルフ・E・ウィンタース |
| 劇映画音楽賞 | ミクロス・ローザ |
| 音響賞 | フランクリン・E・ミルトン |
| 視覚効果賞 | A・アーノルド・ギレスビー/ロバート・マクドナルド/マイロ・ローリー |
『ベン・ハー』はアカデミー賞の歴代最多受賞記録を持つ3作品の1本です。
ちなみに残りの2本は、『タイタニック』(1997年)、『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』(2003年)。
しかしベン・ハーが打ち立てた金字塔は、いまだ揺らぎません。
映画通に「後世に遺したい映画遺産は?」と訊ねたら、この作品を推す人は少なくないでしょう。
なにしろ辟易するほどの仕上がりようですから。
それにつけても、このアメイジングな映像世界はどうでしょう?
2024年に観てもローマ世界に没入してしまう。
最新のCGをつかったスペクタクル映画と比べても見劣りしません。
この時代に観ても観客を飽きさせないなら、100年、200年、いや1000年の風霜にも耐えうる映像なのかもしれない。
1959年版が頭ひとつ抜きん出ている
ルー・ウォーレス原作の『ベン・ハー』は何度も映画化されています。
1907年(15分の短篇)、1925年、そして今作が3度目の映像化。
2003年はアニメ、2016年公開された5度目の『ベン・ハー』は日本では公開されず、Blu-rayとDVD、動画配信で楽しめます。映像は進化したけれども、娯楽作品としての充実度、芸術作品としての完成度ならば、やはり1959年版に一歩譲ることになるでしょう。
『ベン・ハー』といえば、やはりチャールトン・ヘストン主演の1959年が決定版なのかもしれない
本作で大スターになったこの人がアイコンになっているのです。
制作費もレジェンド
お金に面においても『ベン・ハー』はレジェンドの誉れが高い。
今でこそ大作の制作費ならば「1500万ドル」と聞いてもさして驚きはしないが、1950年代では天文学的数字でした。
しかし蓋を開けてみたら、大ヒット。
この作品は、投じた額を補って余りある恵みをMGMにもたらしました。
当時MGMの経営が傾いていたというから、『ベン・ハー』の興行的成功は、まさに神の救済、干天の慈雨になったのです。
書かれた脚本は40本
この作品のために作家たちが書いた脚本の数は40本。
時間をかけて、じっくり腰を据えて、妥協のない作品を創りあげようとする姿勢がうかがえます。
シンプルにして明快、晦渋さのない物語は、ケレン味豊かでしっかりダシが効いている。
子供からおとなまで誰が観ても、映像世界に引き込んでしまう。
212分といっても、退屈なシーンは一切ありません。
スリリングな復讐劇にローマとキリスト史劇でまろやかに味付けしたこの大作の芸術的価値は大きいでしょう。
娯楽作品としても一級品であることは論を俟ちません。
監督ウィリアム・ワイラー~辟易するほど見事な職人芸
監督はウィリアム・ワイラー。
『ミニヴァー夫人』(1942年)、『我等の生涯の最良の年』(1946年)に続く3度目のオスカー受賞です。
押しも押されもせぬ巨匠と言えるでしょう。
忘れてはいけないのは『ローマの休日』(1953年)もワイラーが手がけた作品であること。
つまりこの人は気に入った作品ならば、どんなジャンルでも見事な職人芸で仕上げてしまう。
1925年版では助監督だったワイラーですが、今作で監督になったこの人は軽率な自己模倣を許さず、創造者として自己超克を志向しているようです。時代考証はどこもでも厳密であり、隅々にまで徹底されています。
茶色の水をたたえた池を地中海のブルーにするために、化学の専門家を招き、特殊染料で染め上げたという。
実物大で創り上げた戦車レース場、衣装、小道具、髪型、ひげのたくわえかたに至るまで、監督の神経が行き届いている。
なかんずく、当時のローマ帝国の再現度は辟易するほど素晴らしい出来栄えです。
思わず「ほうっ」と大きく息を洩らしてしまう。
登場人物たちの立ち居振る舞いにも目配りを忘れていません。
(食事のシーンでは、ベン・ハー一家はちゃんとからだを横たえて食事をしていた)
この人には大向うを唸らせる目的だけで小手先の技術を弄する野暮ったさがない。
当時はそんな言葉はなかったにせよ、コスパやタイパという発想はワイラーには縁遠かったでしょう。
なぜなら効率性と創造性とはトレードオフの関係にあるからです。
潤沢な制作費に恵まれていたとはいえ、ウィリアム・ワイラーによる豊かな創造性と卓越した職人芸なしに『ベン・ハー』の映画的達成はありません。6年という制作期間もウィリアム・ワイラーが十分に腕をふるうには長くもなく短くもない時間です。
物語の考察・感想

重厚な人間ドラマ
まずもって大迫力の戦車競走のシーンが最も評価される『ベン・ハー』ですが、ウィリアム・ワイラーの真骨頂はなんといっても「人間ドラマ」でしょう。ワイラーという人の職人芸は、もっぱら重厚な人間劇を創造するために捧げられています。その点、黒澤明のスタイルと通底しているかもしれない。
骨太なスペクタクル活劇に清新な息吹を吹き込み、ノーブルだけれど敷居の高さを感じさせません。
ミクロス・ローザの勇壮で懐の深い音楽にも静かに心の襞に沁みこんでゆく。
ベン・ハーと宿敵メッサラとの対立と復讐劇は見ごたえたっぷり。
一神教と多神教の確執を描く監督の手さばきはあざやか。
ユダヤとローマの確執を単純化せず、冷徹なまなざしで描きったところにワイラーのこだわりがうかがえます。
主人公の家族、最愛の人エスター、養父の執政官アリウス、族長イルデリムに、総督ピラトゥス ━━ 登場人物たちの個性は見事に粒立ってい、キャラクターの描き込みにも余念がありません。
人物たちがいきいきと活気づいているから、豪華なセットや入念な時代考証が浮華にならずに地に足がついている。
人も舞台装置も道具立てにも、ワイラー監督の脈打つ気概が感じられて、つい威儀を正してしまいます。
前半では海戦あり、後半では戦車競争あり、ワイルドで猛々しい作品だけれども、ときおりナイーブさも感じさせるのが心憎い。作品の持つ懐の深さや光沢や艶の秘密はそのあたりにあるのかもしれません。
イエス・キリストの描き方に艶がある
主人公ベン・ハーとほぼ同じ年齢としてイエス・キリストが描かれています。
序盤、死にかけたベン・ハーに一杯の水を与えた人として登場。
カメラはキリストを正面からとらえない。遠望で正面を映すとしても、顔かたちは判然としないぶん神々しさは伝わってくる。
それにしても、なんと艶のあるキリストの描き方なんでしょう。
ナザレの大工の息子のたたずまいには、一種の雰囲気があって、ここにもワイラー監督の妙技の冴えが感じられます。
物語終盤、キリストの磔刑後、神の怒りを象徴するように太陽がその光を失い、不思議な現象が起こる。
福音書の描写どおり。
ロマンスよりも家族愛
特筆に値するのは、『ベン・ハー』は家族愛に重きを置いていること。
たしかにベン・ハーとエスターによるロマンスの比重が大きくなると、この物語の求心力は乏しくなるでしょう。作品としての均衡が損なわれ、重心がぐらつき、おさまりが悪くなっていたかもしれない。家族愛を描いて正解だったようです。
主人公は教条主義的な正義を振りかざす性向もなくはないが、母と妹を気づかう端正なあたたかさを持っています。
母と妹もまた、ベン・ハーを思いやる心だてが美しく描かれている。
至純という言葉がふさわしい、まじりけなしの情愛に心が揺さぶられます。
聖史劇に一家族の情愛ドラマを重ね合わせたことで、この作品は普遍的な高みにまで昇華されているようです。
ラストは何度も観ても、辟易するほど涙がこみあげてくる。
宗教的感動、宗教的愉悦と言ってもいいかもしれない。
「戦車競走」の感想

映画史に燦然と輝く戦車競走シーンを語らずして、『ベン・ハー』は語れません。
後年のアクション映画のカーチェイスシーンに影響を与えているほどです。
このレースのためにこしらえたレース場は、『ベン・ハー』一作のために存在し、撮影終了後には破壊されたという。
亜流の量産を認めなかったのかもしれません。
出場9台の戦車は、ローマ、アレクサンドリア、アテネ、カルタゴ、キプロス、コリント、フリジア、メッシナ、そして、ベン・ハーは代表のユダヤ。4頭立ての戦車だから36頭の馬が、砂煙を蹴立てて所狭しと激突するレースには度肝を抜かれる。
ロバート・L・サーティースのカメラワークは実にすばらしく、首尾結構のととのった作品世界はこの人の撮影技術に負うところが大きいです。むろんCGもVFXもありません。生身の人馬が抜いたり抜かれたり、ぶつかったりぶつからなかったり、御者が落馬したり他の戦車に轢かれたりするのだから目が離せない。スタントマンも命がけの仕事だったでしょう。
ベン・ハーの白馬と、メッサラの黒馬のコントラストも絶妙。
メッサラが御する戦車の車軸には鋭利なドリル状の刃物が「シャキーン」と突き出してい、近寄る戦車に修復のきかないダメージを与える。永井豪氏のロボットアニメを彷彿とさせる「シャキーン」です。いかにもローマ的アロガンスを象徴した趣向。
ベン・ハーの戦車も「シャキーン」な刃物に苦戦を強いられるが、なんとか体勢を持ちこたえてメッサラとの激しい接戦が繰り広げられる。最後はベンとメッサラが競走しているというより、ひとつにユニットになって映画史に残る芸術的デッドヒートを「共創」しているかのようです。この緊迫感には思わず身悶えしてしまう。
レースの勝敗の行方はネタばらしになるため書かないでおきますが、ローマ帝国が市民に提供した「パンとサーカス」におけるサーカスは、2,000年後もその娯楽性はいささかも古びていません。剣闘士の試合にせよ、戦車競走にせよ、人間の本能をくすぐるような愉悦のツボをおさえています。
ちなみに『ベン・ハー』の戦車競走は徹頭徹尾フィクションです。
史実とはいささか異なります。
| 史実 | 『ベン・ハー』のフィクション | |
|---|---|---|
| 出場台数 | 戦車4台が基本 | 9台 |
| 馬の頭数 | 2頭立てが基本 | 4頭立て (4頭立て競走もあるが、ローマならいざしらず、属州ではまずなかった) |
| 周回回数 | 通常7周 | 9周 |
こういう愉快な脚色は、映画ならでは。
『ベン・ハー』公開当時、多くの観客は戦車競走のシーンだけでも、映画館入場料のもとが取れたと満足したでしょう。
今なら、動画レンタル料、サブスク料金でももとが取れること請け合いです。
『ベン・ハー』のキャストについての考察

チャールトン・ヘストン(ジュダ・ベン・ハー役)
演技の巧拙という基準では推し量れない役者のひとりです。
「存在感がある」という紋切り型の賛辞とも違います。
チャールトン・ヘストンの立ち居振る舞いが史劇や大作に、かっちりとハマる。
それも立派な才能ではないでしょうか。
ヘストンを得たことで、映画『ベン・ハー』は伝説になったといっても過言ではありません。
もしもポール・ニューマンがベン・ハー役のオファーを受けていたならば、この人の役者人生の様相は大きく変わっていたでしょう。
ヘストンの誠実な人柄は、一歩一歩着実に地歩を固めていくような辺幅を飾らない役づくりにうかがえます。
観ていて安心できるのです。
ちょっと “くさめ” な演技も素直に受け入れられるのは、この人の人間性に深く与っているからではないでしょうか。
とくに感傷の断ち切り方には、好ましい “くささ” があふれていて、ハッとさせられてグッとくる。
どこまでも作品に挺身する姿勢から、自身の演技に対する謙虚さがうかがえます。
抒情と奇蹟のバランスを加減しつつ、話を大げさに盛り上げようとはしないので、物語そのものに自然なダイナミズムが生まれて、豊かな起伏を生み出している。
だからチャールトン・ヘストンは史劇や大作に適しているのでしょう。
この人は良くも悪くも不合理を演技に入れて、論理性や合理性の外に「跳躍」するようなヤンチャはやりません。
マーロン・ブランドやジャック・ニコルソン、ロバート・デ・ニーロとは香りが違います。
ヘストンの演技は、狂気と稚気が薄いともいえますが、「侠気」には不足なく、個性を抑える姿を「持ち味」にできる人です。だから鞭打たれるベン・ハーの姿には見るべきものがあります。
半裸で鎖に繋がれている姿もいいですねぇ。なんとも捨てがたい興趣がある。
「俳味」があると申し上げてもいいでしょう。
出演作によって、捕縛する側はローマ兵だったり猿だったりしますが、チャールトン・ヘストンが囚われて肉体を軋ませながら悲嘆に暮れる構図は変わりません。
ガレー船の漕ぎ手となって大きく肩で息をしながら、怖めず臆せず前方を睨んでいるヘストンの姿も異彩を放っています。囚人たちが放つ汗のにおい、熱気、絶望感がこもった船内の空気の肌触りが、ヘストンのたたずまいを通して伝わってくる。
古代ローマという時代設定を割り引いても、やたらと肉体をみせつけるのに辟易させられますが、これもヘストンの “芸風” です。この人の肉体美には持って生まれたセンスがうかがえる。根を詰めてワークアウトしたところで誰にでも手に入る肉体ではありません。
運命に翻弄されていよいよ際立ってくる筋肉は、敏捷な野生動物のように屈強でしなやかですが、ときおり痛みや脆さも感じさせます。インスタ映えはしないけど、銀幕には十二分に映えるエモーショナルな肉体美。
「筋肉は裏切らない」という言葉がありますが、ヘストンの筋肉は「あるいは筋肉は裏切るかもしれないな」と油断ならない気持ちにさせます。
ヘストンの物堅さの裏面には、一度キレたら何をおっぱじめるかわからない危うさも抱えていて、それがベン・ハーという役柄に複雑な輝きを与えているようです。
たしかに英雄ですが、一神教であるがゆえの「価値に多様性は認めない」という一徹さが、言動や立ち居振る舞いにあらわれている。「復讐を勲し」とする気概にも、正義の発露というより人間性のほの暗い冷徹さがうかがえる。
単純な善人ではないからこそ、ベン・ハーは強く印象に残るのでしょう。
あわせて『猿の惑星』も観たくなります。
スティーヴン・ボイド(メッサラ役)
割れ顎がサマになるこの人のローマ司令官姿は凛々しく恰幅がいい。
チャールトン・ヘストンとは趣を異にしますが、この人も身体で演技をするタイプの人かもしれません。
撮影当時ならばまだ20代前半のこの人には、老成した印象があります。
メッサラにはまるで青臭さがなく、手心を加えないアロガンスと老練な官僚臭の漂わせかたが板についている。
「卑しい魅力」でも「魅惑の卑しさ」でもない、スマートな俗物の輝きといえばいいでしょうか。
スティーヴン・ボイドが演じるメッサラは、まさに多神教ローマを体現した人物。
信仰の自由ならばどこまでも寛大なローマ人だから、ユダヤそのものに弾圧を加えたりしません。
ですが、ローマ皇帝に恭順を示さないベン・ハーとは袂を分かってしまう。
ハー家の瓦が新総督の頭上に落ちたのが明らかに事故とわかっても、ローマに楯突く者はたとえ竹馬の友であろうと容赦しません。メッサラの気位の高さを通して、帝政ローマの不人情が観る者の心に届いてきます。
戦車競走でも、スティーヴン・ボイドは素晴らしい演技を見せてくれました。
ベン・ハーとの接戦で焦るメッサラ。ここでこの人はいけないことをします。
馬に向けていた鞭を、横についたベン・ハーに向けてふりあげるのです。
これはアカン。
それだけはやったらアカン。
倫理的にアカンというより、振る舞いとして美しくない。
ところが、美しくない振る舞いがスリリングな異彩を放つのだから「はて面妖な」という心境です。
たんに薄みっともないだけなら印象には残りませんが、なりふり構わずに鞭をふるうメッサラの姿に、ままならぬ人の世の悲哀があふれている。むしろそのようにさせたベン・ハーにも非があるのでは?とメッサラに肩入れしたくなってしまう。
よっぽどメッサラの印象が強かったのか、『ベン・ハー』出演後、スティーヴン・ボイドは史劇や大作に出演しています。
それにしても45歳の死は惜しまれます。
もっと活躍が見たかった俳優です。
ヒュー・グリフィス(族長イルデリム役)
アリウスの養子となったベン・ハーが故郷に帰る途中で出会うアラブの富豪。
諧謔味の少ない作品のなかで、この俳優は、カラフルに艶やかな個性を発揮しています。
味のある名演といってもでしょう。
口の悪さは天下一品、手際の悪い御者を辛辣にこきおろす。
しかしなぜかこの人は憎めない。
胆力、権謀術数、どぎつい野心、どれも不足がなく、嫌味もない。
怪物にでも紳士にでもなれるし、瞬時に切り替えもできるくらいの機知にも富んでいる。
ぶっきらぼうのようでいて、状況への目配りが行き届いているような演技。
繊細さを感じさせる人。
ヒュー・グリフィスの演技の切れ味は爽快です。
カミソリではなく、刃渡り60cmはある鉈の切れ味。
“演技の定型” をばっさばっさと切り裂いていく。
しかも腰が据わって、重心が低い。
映画の前半、忘れがたいシーンがあります。
族長イルデリムがごちそうをもてなしたあと、ベン・ハーに「げっぷ」を催促するのです。
アラブではそれが適切な社交上のマナーなのかもしれない。
それにしても、イルデリムのまなざしがなんともチャーミングでした。
ハイヤ・ハラリート(エスター役)
ハー家に使える執事の娘。
この映画のヒロインであり、ベン・ハーとエスターは相思相愛の仲ですが、ロマンスは色味は乏しい。
そのせいか、エスターの存在はこの物語のアクセントにはなっているものの、なんとなくとってつけた感じが否めません。さればといってヒロイン不在では「華」に欠ける。
脚本家の苦慮がしのばれます。
ハイヤ・ハラリートはイスラエルの俳優で、出演作品は少ないようです。
貧しい女性の役柄でも、拭いきれない品格がうかがえる。
単純な色っぽさではなく、この人の人間からにじみでる色気と艶めきにときおり眩惑されました。
ノーブルで健全な女盛りをとらえるウィリアム・ワイラーの卓絶した手腕のなせる業なのでしょう。
清楚な慎ましやかなエスターもいいけど、この人が演じるファム・ファタール(魔性の女)も背筋が凍るほどの凄味があるかもしれない。
ジャック・ホーキンス(クイントゥス・アリウス役)
ローマの執政官にして、海軍の総司令官。
ガレー船に送られたベン・ハーの捨て身の救出によって九死に一生を得たアリウスは、ベン・ハーを養子に迎える。
そんな予定調和を担うこの人の演技によって、物語は淀みなく進みます。
とりわけ強く印象に残っているのが、船の中でアリウスがベン・ハーの背中に鞭打つシーン。
チャールトン・ヘストンの苦痛の歪む表情を引き出させたジャック・ホーキンスの冷徹さがきらりと光ります。
収容迫らぬたたずまいと、ノブリス・オブリージュを体現したかの如き押し出しの強さは見事。
自信のない男なら、へえつくばってしまうでしょう。
ジャック・ホーキンスもまた、歴史もの、大作ものに映える役者です。
デビッド・リーン監督作品『戦場にかける橋』『アラビアのロレンス』でも存在感を示しています。
フランク・スリング(ポンテオ・ピラトゥス役)
アリウスの友人であり、イエスを処刑した属州ユダヤの総督。
この身のこなし、立ち姿はどうだろう。
総督がまとう衣装の高飛車なドレープ感がこなれている。
堅苦しくなく、ゆったりしたシルエットだが、帝政初期ローマのアロガンスには不足はない。
洗練の極みを尽くした高貴なる高慢ちきですが、なぜか嫌悪感は薄められています。
情念は感じられないため超俗した印象は強いわりには、きらめくようなウィットは人間味たっぷり。
帝政ローマを非難するベン・ハーに対し、ピラトゥスが「過ちも大きいが失敗を糧にして発展する」と眉一つ動かさず擁護する場面は、洒脱なセンスを感じさせる。
マーサ・スコット(ミリアム役)
ベン・ハーの母を心を込めて演じています。
苦難にさいなまれようとも端正さを失いません。
声の潤ませかたに、高い演技力が垣間見えます。
この人を見ていると、なぜか思い起こされるのが山岡久乃さん。
似ているというより同じタイプの役者のように感じます。
キャシー・オドネル(ティルザ役)
ベン・ハーの妹を甲斐甲斐しく扮演。
清潔感あふれる存在感で、やや臭めなセリフや取り澄ました身振りもチャーミングです。
だが、この人には俗情に媚びない芯の強さが感じられて、マイルドなセクシーさがうかがえる。
この人を見てイメージする日本の女優は、『岸辺のアルバム』に出演していた頃の中田喜子さん。
《コラム》歴史・物語・虚実皮膜

『ベン・ハー』は、現代の日本とは時代も距離も隔たること遠い物語である。
しかし人間の種々相、人びとの生のありようは、ティベリウス帝がおさめた帝政ローマと、民主主義の現代日本とさしたる違いはない。
ベン・ハーとメッサラの確執のなかに、人間関係のままならさを投影する人もいるだろう。
ベン・ハー一家のこまやかな家族愛に、自分の家族の姿を重ね合わせる人も少なくない。
いつのまにか、ローマの時代やキリスト教への興味関心が駆動しているという寸法だ。
がぜん歴史が楽しくなる。
教科書でお勉強した歴史はつまらないのに、なぜ小説や映画を通して触れる歴史はすこぶるおもしろいのだろう?
やはり叙述形式に負うところは大きいのではないだろうか。
歴史というのは、年表を暗記させられた段階でその意義を大きく失うのかもしれない。
暗記するまでもなく、人それぞれ人生の困難に直面したときに、歴史のなかに自分を投影するからだ。
歴史を自分ごととして近寄せるには、己を投影できる「物語」という装置が好適である。
異なる時代、異なる文化、異なる宗教のなかの登場人物に感情移入し、人生を追体験するうちに思い至るのだ。
「自分の外に歴史があるのではなく、自分そのものが歴史なのだ」という真理に。
優れた物語ほど、虚実皮膜の “あわい” に生み出されるのではないだろうか。
虚構と史実の間を行ったり来たりする物語ほど、歴史が肌身にそくそくと迫ってくる。
歴史が自己に肉薄してくるのだ。
ベン・ハーやメッサラは架空の人物だが、彼らは実在していたと言われても、ちっとも驚かない。
モデルはいるかもしれないが、1世紀のローマ時代に実際に起こった事件と言われても怪しむに足りないリアリティをたたえている。
プロフェッショナルによる一意専心の仕事によって成し遂げられた歴史映画に、虚構とリアルの線引きほど野暮ったいものはない。歴史と自己が混じり合うように、虚構とリアルの渾然一体こそ「実相」と言えまいか。
『ベン・ハー』のような魅力あふれる歴史物語に触れるとき、論理や理屈を超えて感得する。
虚実皮膜こそが世界なのだ、と。
さいごに~『ベン・ハー』の動画を配信しているサービスは?
『ベン・ハー』は以下にあてはまる方におすすめ
- 歴史映画がお好みの方
-
1世紀頃の古代ローマの社会やキリスト教発祥の歴史に興味がある方なら、『ベン・ハー』の映像世界は興味が尽きないでしょう。ことにローマ帝国の属州民に対する支配の描出はリアリティがあります。
丹念かつ緻密な歴史考証に裏付けられた壮大なセットや美しい衣装も一見の価値あり! - 大迫力のスペクタル・アクションシーンに目がない方
-
戦車競走のシーンは映画ファンでなくても観ておいて損はありません。何が素晴らしいといって、ほぼ実写による映像のダイナミズムと緊迫感。知らず知らずのうちにのめりこんで手に汗握ってしまうほど。部分的には特殊撮影があるものの、「どうやって撮影したんだろう?」と驚きを禁じえません。
- 重厚な人間関係の物語がお好みの方
-
ベン・ハーとメッサラの友情と反目、家族の絆 ━━ 普遍的な人間ドラマにどっぷり感情移入してしまうでしょう。
- アカデミー賞の歴代最多受賞作品をチェックしたい方
-
長時間の作品ですが、11部門でのアカデミー賞受賞作品だけあって、面白さには説得力があります。
この機会に、『ベン・ハー』をご覧ください。
意外と泣けるんです。そりゃもう、辟易するほど……。