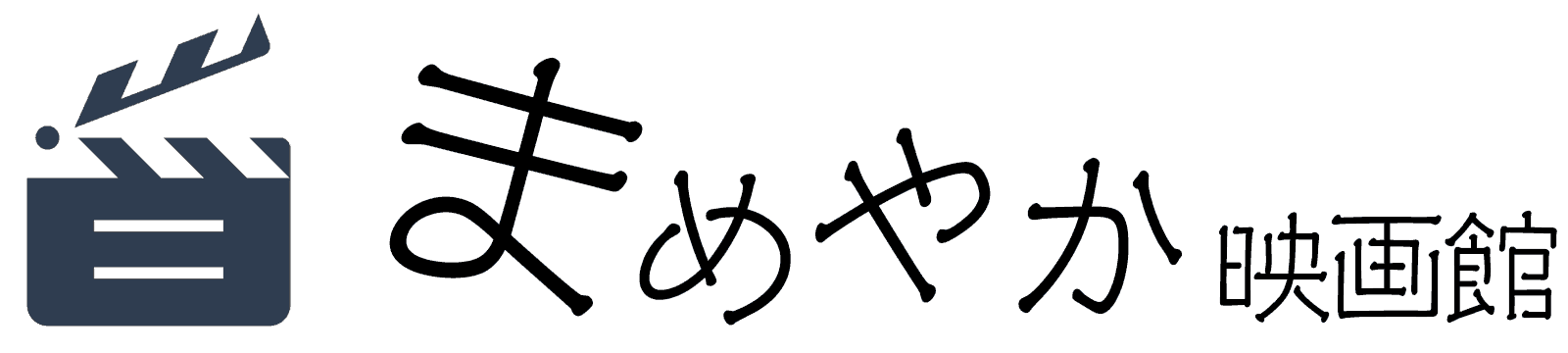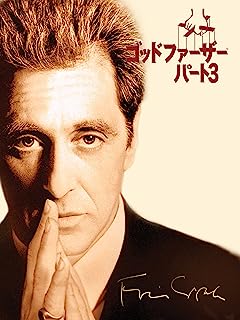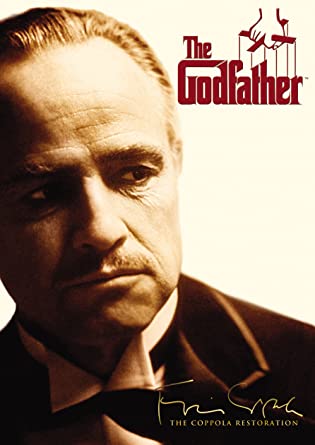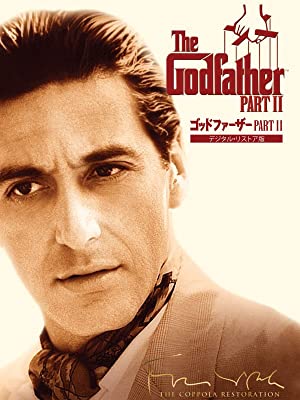『市民ケーン』(1941年)
主演:オーソン・ウェルズ /ジョゼフ・コットン/ドロシー・カミンゴア
原題:Citizen Kane
アメリカ映画史上最高傑作との誉れ高い名作『市民ケーン』。巨万の富に恵まれながらも、空虚な人生を歩み続け、最期に謎の言葉を遺してこの世を去る新聞王のあまりにも孤独な生涯をミステリー仕立てで描く。制作・共同脚本・主演をこなしたオーソン・ウェルズは若干25歳。処女作にして頂点をきわめたかのような『市民ケーン』の解説・感想・考察を綴ります。
- 『市民ケーン』のあらすじは?
- 「史上最高の映画」と言われるゆえんを知りたい!
- 『市民ケーン』のみどころは?解説・感想を教えて!
- 主要キャストの魅力は?考察が聞きたい!

『市民ケーン』作品情報

| 監督・制作 | オーソン・ウェルズ |
| 脚本 | ハーマン・J・マンキーウィッツ/オーソン・ウェルズ |
| 撮影 | グレッグ・トーランド |
| 音楽 | バーナード・ハーマン |
| 編集 | ロバート・ワイズ |
| 特殊効果 | ヴァーノン・L・ウォーカー |
| 出演 | ケーン・・・オーソン・ウェルズ リーランド・・・ジョゼフ・コットン スーザン・・・ドロシー・カミンゴア エミリー・・・ ルース・ウォリック バーンステイン・・・エヴェレット・スローン ゲティス: レイ・・・コリンズ サッチャー: ジョージ・クールリス メアリー・ケーン・・・グネス・ムーアヘッド レイモンド・・・ポール・スチュアート |
| 上映時間 | 119分 |
| ジャンル | サスペンス/ミステリー/諷刺劇 |
『市民ケーン』のあらすじ
「ローズバッド」(バラのつぼみ) ━━
アメリカの新聞王、チャールズ・フォスター・ケーンが息絶える前に遺した謎の言葉である。手に握られたスノードームは、持ち主の死と同時に転がり落ちて割れてしまう。終の住処となったその巨大で虚ろな邸宅は「ザナドゥ城」と呼ばれ、ケーンの晩年は深い孤独のうちに沈み込んでいた。
ニュース映画の中では、新聞王ケーンの死を伝えるとともに、その起伏に富んだ生涯が紹介される。ニュース映画会社は首脳陣は、ケーンのダイイング・メッセージともとれる「ローズバッド」の意味を明らかにすることで、新聞王の実像に肉薄できる考え、記者トンプソンに調査を命じる。
トンプソンは、酒場で酔いつぶれ身を持ち崩した、ケーンの二度目の妻スーザンや、ケーンのビジネス上のパートナーであるバーンステイン、さらにケーンの親友であったリーランド、ケーンの終の住処であるザナドゥの執事へ取材。少しずつ、新聞王ケーンの栄光と孤独の人生が重層的に明らかにされてゆく。
幼少の頃ケーンは、下宿屋を生業としていた両親は財産相続をめぐって、愛する母と離別。後見人にして銀行家であるサッチャーのもとで育てられる。
25歳にして、世界第6位の資産家になったケーンは、サッチャーの猛反対を意に介さず、小さな新聞社インクワイラーを買収。俗受けを狙ったセンセーショナルな記事で部数を伸ばし、「言論」を牛耳って時代の寵児に。
大統領の姪エミリーと結婚したケーンだが、妻とウマが合わないために夫婦関係はしだいに冷めていく。そんななか州知事に立候補。ライバルであるゲティスをこっぴどくやっつけ排除しようと目論むが、歌手志望の愛人スーザンとのスキャンダルを暴かれ、選挙に敗北。エミリーにも愛想を尽かされる。
スーザンと再婚したケーンは、彼女のためにオペラハウスを建てて、妻を歌手として一人前にしようと画策。だがスーザンはオペラ歌手としての実力を著しく欠いていたために酷評されて世間の笑いものに。友人であり劇評家であるリーランドは、ケーンについて行けず袂を分かつ。
スーザンもケーンの独善的な愛に堪えきれず鎮痛剤を過剰に服用し昏倒。ケーンはやむなく妻の歌手としてのサクセスを断念する。だがスーザンの不幸は続く。ケーンの邸宅であるザナドゥ城での生活は、籠の中の鳥そのものだった。ついにスーザンもケーンの元から去ってしまう。
絶望的な孤独の只中に取り残され、空虚なザナドゥで最期を迎えたケーンの胸中に秘していた想いは誰にもわからないままだ。関係者から証言を拾い集めたものの、トンプソンは依然として「ローズバット」のメッセージに込められたミステリーは解明できずにいた。
だがトンプソンがザナドゥ城の邸宅を訪れたときに、「ローズバッド」の謎が観客に明かされる……
『市民ケーン』の解説と感想、考察

襟裳岬と市民ケーン
ケッタイな見出しをつけてしまい申し訳ありません。
なぜか、映画『市民ケーン』を思い出すと、森進一の『襟裳岬』が頭の中で流れるのです。その逆もまた真なりで、『襟裳岬』を聴くと、『市民ケーン』のシーンが浮かび上がる。なぜだろう?
このわりかしどうでもいい “妙ちきりん” な現象について、勝手な解釈を試みたいと思います。
『襟裳岬』と『市民ケーン』が持つ世界観の類似点
『襟裳岬』の歌詞にある「襟裳の春は何もない春です」という一節。
あたかもオーソン・ウェルズが演じるケーンの晩年を象徴するかのようです。ケーンの人生は、外見上は華やかで成功を収めたものの、内面は「何もない春」と形容できるような、名状しがたい悲しみと虚無感に満ちている。このうら悲しさが、『市民ケーン』と『襟裳岬』を繋いでいるように感じるのです。
両作品に共通する感傷やペーソス
『襟裳岬』も『市民ケーン』も愛惜の念を呼び起こす作品であることはあなたも同意していただけるでしょう。
過ぎ去った日々に対する、えも言われぬ悲哀は、甘たるいノスタルジーに浸って消えるものではありません。他者にも共感され、価値を見出される感情へと昇華されます。両作品は人間の深層に迫る力を持っていると言ってもいいでしょう。
個々人が作品から受ける印象の多様性
僕が『市民ケーン』を観て『襟裳岬』を思い起こすのは個人的な体験に基づくものですが、他の人には全く異なる音楽や映像が『市民ケーン』と関連付けられるかもしれません。たとえば、『おふくろさん』であるかもしれないし、五木ひろしの『よこはま・たそがれ』や細川たかしの『浪花節だよ人生は』のような曲かもしれない。『市民ケーン』とはまったく関係のないジャンルでも、何かしらの作品が同様の感情を喚起させる。そういう不思議な喚起力を内に秘めた映画が『市民ケーン』なのです。
映画『市民ケーン』と『襟裳岬』という一見関連しない作品が、どのようにして個人的な感情や記憶に深く結びつくのか、その不思議な関係性について述べてみました。ちなみに、僕はまだ襟裳岬を訪れたことがありませんが、いつか訪れた際には『市民ケーン』のシーンが思い出されるだろうと想像しています。
時代を超える映画のマスターピース、批評家が選ぶ歴史上最も優れた映画
オーソン・ウェルズの処女作『市民ケーン』は、1942年に開催された第14回アカデミー賞で脚本賞(ハーマン・J・マンキウィッツとオーソン・ウェルズ)を受賞。公開当時、この映画は不遇をかこっていたけれども、時間が経つにつれてその真価が正当に認められるようになりました。
特筆さるべきは、英国映画協会が10年ごとに発表する「批評家が選ぶ最も優れた映画」- The Critics’ Top 50 Greatest Films of All Time -で、『市民ケーン』が1962年から5回連続で1位に選出された事実。まさに時代を超えたマスターピース(名作・傑作)であることを示しています。
そんなにすごい作品とわかれば、人間の習性として、色眼鏡をかけてしまうのは致し方ありません。やたらとディテールが目について「おお!すごい!」と再発見することおびただしい。光と影の演出は冴えわたってい、その緻密に計算された映像とストーリーのテンポ、リズムに「さすが名作は一味違うな!」と心地よく酩酊してしまうのです。
でもマスターピースってそういうものじゃないでしょうか。たとえ色眼鏡を装着しても、人々の心を打つならば、マスターピースとしての本分を十分果たしているのではあるまいか。もし色眼鏡を外せたとしても、オーソン・ウェルズが映画界に登場した時、その才能と『市民ケーン』の完成度に多くの人が驚愕したのはまごうかたなき事実です。しかし、その新しさと革新性ゆえに、風当たりも格別強かったのは否めません。
凄まじい逆境のなかで磨き抜かれた名作
『市民ケーン』の制作と公開の過程は、凄まじい逆境の連続でした。
刺激の強いキャラクター
まず、映画の中心人物であるチャールズ・フォスター・ケーンは、資本家からコミュニストと揶揄され、労働者からはファシストと非難されるなど、ニューディール時代のポピュリズムを体現した人物として描かれます。この複雑なキャラクター設定は、政治的に刺激が強く、多様な解釈を促したのは想像に難くありません。不快と嫌悪を露わにした人も少なくないでしょう。
実在の新聞王の逆鱗に触れる
『市民ケーン』の主人公が、新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストをモデルにしたことは、多大な反響を呼びました。とりわけ、この映画を読み解くキーワードである「ローズバッド」(バラのつぼみ)がいけなかった。ハーストの愛人にして女優のマリオン・デイヴィスの秘部の暗喩であるという。「そんなん考えすぎやろ!」と思わず首を傾げてしまいますが、これも現代人の感覚なのかもしれません。とまれ、怒り心頭に発したハーストは、マスメディアを使って『市民ケーン』を徹底的に叩きます。上映妨害と言っても差し支えないでしょう。
業界内からも反発
さらにMGMの首脳であるルイス・B・メイヤーが『市民ケーン』を「反アメリカ、反ハリウッド」と非難。映画の全てのネガとプリントの廃棄を求めるなど、業界内からも強い反発を招きました。アカデミー賞の授賞式では、『市民ケーン』の名前が呼ばれるたびに客席からブーイングを起きるという嫌われっぷり。
でも考えてみたら、こうした逆境が、『市民ケーン』の普遍性と卓越性をより一層際立たせたのではないでしょうか。
数々の不遇と困難は、作品が時代を超えて語り継がれる名作となるための試練であったと言えます。凡庸な作品ならば、これほどまでに注目されることはなかったでしょう。
一筆感想

革新的な撮影技法「パンフォーカス」
『市民ケーン』は、その撮影技術においても映画史に残る画期的な映像芸術です。
カメラマンのグレッグ・トーランドが駆使した撮影技法「パンフォーカス」は、映画製作における新たな地平を開きました。
パンフォーカスとは、画面に映る前景、中景、背景のすべての被写体を同時にピント合わせすることで、全てをクリアカットに見せる技術。
例えば、ケーンの幼少期を描いたネブラスカの家のシーンで、この技法の効果が顕著に表れています。
前景 ━━《屋内》銀行家と母親
中景 ━━《屋内》父親
背景 ━━《屋外》雪の中、外で遊ぶケーン
一つのフレーム内で、屋内にいる人物たちと、窓の外でソリで遊ぶケーン少年が同時に映し出される。
近景と遠景が同時にくっきりと見えるため、非常にダイナミックな映像表現を実現しています。
パンフォーカスにより、通常ならば複数のカットに分けて描かれるシーンも、一つのカットで効果的に表現することができました。結果として、観客は一目で物語の状況を把握できるようになり、映像から得られる情報量が飛躍的に増加したのです。
『市民ケーン』の撮影技術、特にパンフォーカスは、映画製作における創造性の極致を示すものです。
きょうび、感度の高いカメラを使用して容易に実現できるパンフォーカスも、『市民ケーン』が制作された時代には、技術的な挑戦と革新を要求するものでした。後進の映画人のクリエイティビティを賦活させたことでしょう。
その迫力満点で緻密に計算された映像はもとより、オーソン・ウェルズとグレッグ・トーランドの妥協のない仕事ぶりに、ただただ唸らされます。
虚実皮膜のおかしみを味わう、上質な人間ミステリー
『市民ケーン』は、虚実が巧みに交錯する上質な人間ミステリーの傑作です。
記者トンプソンが、新聞ケーンの遺した言葉「ローズバッド」の謎を追うミステリー仕立てで物語は進行します。緊張と弛緩のメリハリが効かせながら、言論と富を手に入れながらも孤独に死んだ男の生涯をたどることで、2時間飽きることなく最後まで視聴者を画面に釘付けにする。
それだけなら並の作品ですが、『市民ケーン』が一頭地を抜いているのは、独特の諷刺精神と深い人間ドラマを通じて、観る者を引き込む吸引力が半端ではないということ。冒頭部分に挿入されたニュースフィルムの使用は実にうまい。インサートの仕方がまったく不自然ではありません。映画の独特の雰囲気をあたえ、隙のないほど整序されていることで類を見ない諷刺精神をたたえた物語に仕上げられている。実際の新聞王ハーストをモデルにしていることで、虚実皮膜のおかしみは一層深まるのです。
オーソン・ウェルズの創造力と劇作術には、「真摯に人を食った精神」が横溢していて、観ているこちらも愉快な気分にさせられます。若干25歳の早熟の天才は、商業性に尻尾をふるような野暮をおかしていません。ひとつひとつのシーンに前衛の気概が脈打ち、俗情に媚びるところはない。独善的なスタイルの貫徹を恐れていない。
だからこそ、新聞王ケーンの独善も十二分にギャラントな魅力をたたえている。道義や常識よりも、己の野心を優先させた人間があじわう、パッションのむなしさと痛切なまでの孤独には詩情さえあれふれていて、滋味掬すべきものがある。たとえその才能の向かう先が喪失以外にないとわかっているからこそ、ケーンに嫌悪は感じない。彼に共感はできないにしても、その運命を最後まで静かに敬意をもって見届けたくなる。
『市民ケーン』は、その革新的な撮影技法と物語構成、深い人間性の探求によって、エンターテインメント作品としても、人間ミステリーとしても申し分のない作品です。虚実皮膜の妙味を味わいたい方には、一見の価値ある映画と言えるでしょう。
『市民ケーン』の主要キャストに対する感想レビュー

オーソン・ウェルズ(チャールズ・フォスター・ケーン役)
早咲きにすぎる天才 ━━
周囲の手に余る傑物 ━━
野性を内包した知性 ━━
この人は実にいろんなキャッチフレーズをつけやすい人です。威風堂々、二十数年しか生きていない人とは思えぬ貫禄と達観、己の力動に率直に従う率直さ、この人の溢れ出るパワーには刮目すべきものがある。
オーソン・ウェルズの人間的魅力に大きく寄与しているのは、卓抜した知性です。ただの頭のいい役者ではなく本物の知識人である明白な証拠が、先鋭的な映画作りのスタイルやセリフから見て取れます。
多くの才気溢れたクリエイターがそうであるように、オーソン・ウェルズも、その類まれな資質から独善性だけを取り除くことは出来ない相談です。謙虚さを見せる必要はないし、エゴを抑えこまなくてもいい。彼のギャラントな独善の迸りをファンは観ていたいのです。
独特の風貌もインパクㇳがあるけれども、あの深く温かみのあるバリトンは、どれだけ言葉を尽くして安心感を与えても、宿命的に不穏な響きは完全に払拭できません。ゆえにこの人の存在感は忘れがたいのです。
オーソン・ウェルズ演じるケーンの野心に健全さは感じられない。気品はあるが、濁りがある。屈託は薄いが、屈折を感じさせる。鼻持ちならない人間ではあるけれど、なぜか人の心をつかんで揺り動かす不思議な人徳を持っている。
出演している俳優たちのほとんどがすべてが初出演であり、彼が率いる劇団のメンバーたちです。撮影現場ではきっと、オーソン・ウェルズは辣腕をふるったことでしょう。なにしろ実験精神を大切にした人だから、なかには彼のやり方に難色を示したかもしれません。
思うにオーソン・ウェルズは「理」を説くというより、理屈を越えて「情」に訴えるというタイプではないかと。理屈を越えた情への訴求が、彼の作品に生命を吹き込んでいます。でなければ、当時、これだけの規格外の映画は作れなかったでしょう。
惜しむらくは、オーソン・ウェルズが自由に采配をふるう機会が二度と与えられなかったこと。『市民ケーン』以後は、『第三の男』や『オーソン・ウェルズのオセロ』など、映画史に残る傑作を生み出しています。しかし、『市民ケーン』制作時のような自由な立場を彼に再び与えてほしかったと無念に思うファンは少なくないでしょう。
言っても(書いても)詮無いことですけど、この人の天稟にふさわしい立場を与えてあげれば、映画史が変わっていたかもしれません。あたら才能を空費した ━━ とまでは言わないけど、オーソン・ウェルズという怪物を、ウヰスキーのCMに起用し飲んべえの日本人を増やしたり、英語教材の声優に起用して日本人のリスニング能力を向上させたりするだけでは、あまりにも……。
重ね重ね思うのは、ウェルズの自身の人生は、ケーンの人生をなぞっているように見えてしまう。その類まれな才能が、最終的に喪失を求めるしかないのかという悲哀がこみあげてくる。
ジャンヌ・モローが述べた言葉は実相を言い当てていて身に沁みます。
「私にはオーソンが見放された王に見えた。この世には彼に見合う王国がないの」
ドキュメンタリー映画『映像の魔術師 オーソン・ウェルズ』より
ジョゼフ・コットン(ジェデッドアイア・リーランド役)
ケーンの親友であり劇評家でもあるリーランドは、ケーンの怪物性を鮮やかに浮き出させる存在です。となれば『第三の男』と同じだけれど、こちらのジョゼフ・コットンは、静謐なパトスをうちに秘めている。ジェントルとインテリジェンスにも不足はありません。
オーソン・ウェルズが一点集中型のタイプなら、この人は散漫でどこかばらけた印象があります。オーソン・ウェルズが「魔王」なら、ジョゼフ・コットンは「スマートな知能犯」といったところか。
線の細い二枚目、覇気を欠いたかっこよさがこの人の魅力。ある種の消極性から生まれる「美質」を持っている。
思わず目を引いたのは、晩年のリーランド。この人の存在感がピリッと際立ちます。トンプソン記者が病院にいる年老いたリーランドを訪ねてインタビューするのだけども、愉快な不良老人になっているのが面白い。辛辣にして饒舌、ハッとするような機知をのぞかせる。絶縁したケーンへの屈託をアイロニーをまぶしながら語る表情は、リーランドもまた人生の辛酸をなめてきたことがうかがえる。
「記憶は人類に与えられた最大ののろいだ」
『市民ケーン』より
このセリフには格別な味わいがある。
ドロシー・カミンゴア(スーザン・アレクサンダー役)
ケーンの2番目の妻。
トンプソンが訪ねたときのスーザンはすっかり身を持ち崩しているが、十分にコケティッシュな魅力をたたえている。
繊細さとハスッパさが入り混じった女が漂わせる哀感にグッときます。
ケーンと結婚して、幸せの絶頂かと想いきや、歌手としての資質がないのに、豪勢なオペラハウスを用意されて舞台に立たされる。お膳立てが立派なだけに、スーザンの歌手としての未熟さがいよいよ露呈する。世間の笑いものになっていく彼女は、ケーンを憎み、孤独に心身を蝕まれていく。
精神のバランスを崩していく姿は、まったくわざとらしくなく、この人が高い演技力をもつことを示しています。ザナドゥ城の色褪せた暮らしに嫌気がさした彼女が「あなたは自分を愛してもらいたいだけなのよ」と夫を詰るシーンは、観ていて術無い心持ちになってくる。
鎮静剤を服用して自殺を企てる場面で、手前にグラス、うしろにスーザン、部屋にケーンが入ってくるシーンは「パンフォーカス」が効果を発揮していてすこぶる印象深い。
新聞王の歪んだ愛情表現から考える「献身のかたちを借りたエゴ」~『市民ケーン』コラム
新聞王ケーンは、明らかに妻への愛情表現に問題ある男である。
2度目の妻スーザンが歌手として不適なのは誰の目にも明らかなのに公演をやめさせない。虐待と言ってもいいだろう。
スーザンが真に望むことを無視して、ケーンの考えるひとりよがりな「スーザンの望み」を金に飽かして実現しようとする姿は哀れを催す。己の立場や外聞を憚るためという理由もあるが、彼なりの歪んだ献身と言えなくもない。献身のかたちを借りたエゴ。あるいはエゴの表現としての献身といえようか。
もしもケーンがスーザンの立場なら、ステージに立ち続けたのかもしれない。「今は酷評されているが、早く実力をつけて見返してやろう」と。ケーンならありそうなことである。
だが、誰もがケーンのように考えるわけではない。ケーンのように図太く馬鹿げたメンタルの持ち主ではないのだ。この哀しい彼我の断絶が、『市民ケーン』の悲劇性を際立たせている。幼少の頃、父母との別れによる喪失が、ケーンの愛情表現を歪(いびつ)にしてしまったのかもしれない。
ケーン夫妻ほど極端ではないにせよ、我々の人間関係にも往々にして「哀しい彼我の断絶」見受けられるのではないだろうか? 相手が真に望むことを無視して、自分の考えるひとりよがりな「相手の望み」を叶えようとしてはいないだろうか。つい忘れがちだけれど、自分がしてもらいこと、自分がされて平気なことでも、相手には迷惑千万かもしれない。もしも、それが献身のかたちをとったらどうなるか? 相手にはエゴの押し付けとして受け入れがたいものになるのは明白だ。
『市民ケーン』は、相手に対する親切心や愛情表現が自己完結していないか、再考する機会を与えてくれる。
さいごに~『市民ケーン』はこんなあなたにおすすめ!
『市民ケーン』は以下にあてはまる方におすすめの映画です。
名作映画を求める人
「史上最高の映画」としばしば称される作品を体験したいという好奇心と、この映画が映画史においてなぜこれほど重要なのかを理解したいあなたに。
ミステリー好きな人
新聞王チャールズ・フォスター・ケーンの死と、彼の最後の言葉「ローズバッド」の謎を中心に展開する物語は、古さを感じさせないほどスリリング。彼の複雑な人格、野心、孤独が徐々に明らかにされていく過程は見応えたっぷり。
濃密な人間ドラマが好きな人
チャールズ・フォスター・ケーンの複雑な個性と愛、権力、アイデンティティへの追求を探るドラマの展開に見応えを感じるでしょう。
映画を学ぶ人および映画製作者志望者
革命的な撮影技術、物語性の構造、ストーリーテリングの使用により、『市民ケーン』は映画学校でよく研究されている作品のひとつ。映画製作者志望者や学生の方は、オーソン・ウェルズの作家性や物語のアプローチから学ぶことが多いことでしょう。
※ただし時期によっては『市民ケーン』の配信およびレンタル期間が終了している可能性があります。