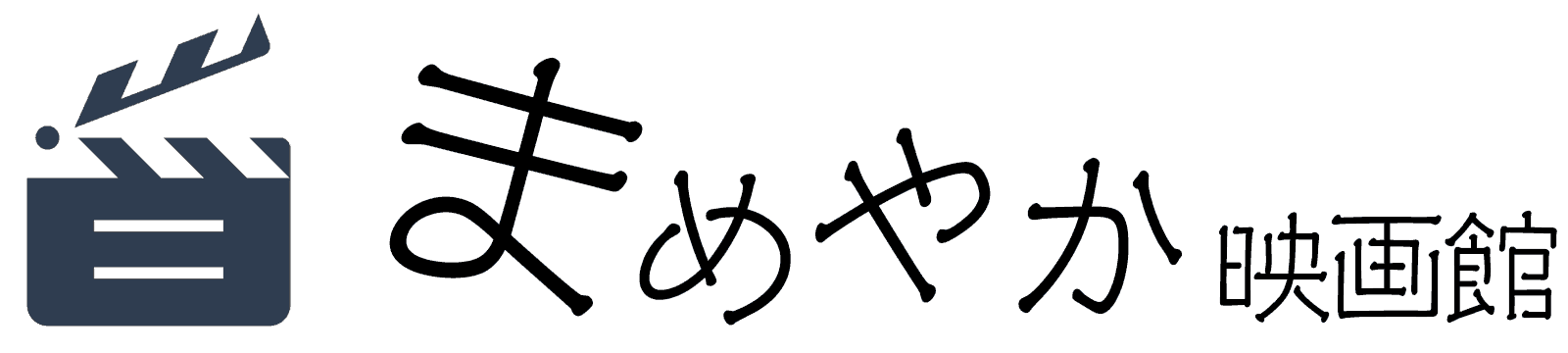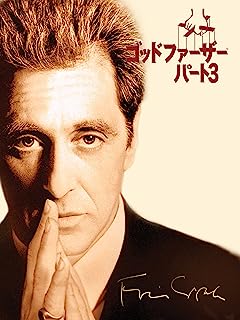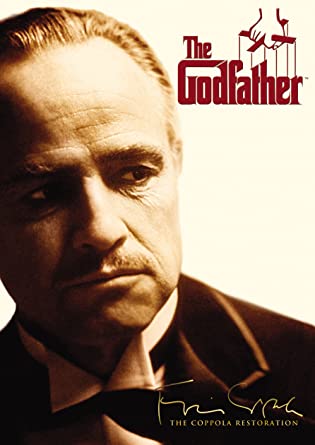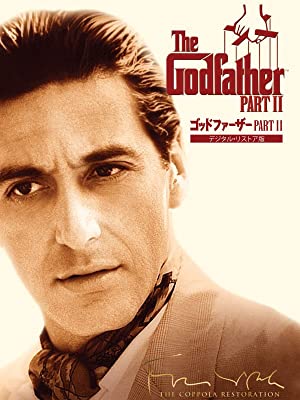『十二人の怒れる男』(1957年)
主演:ヘンリー・フォンダ
もともとテレビドラマの作品を、主役を務めるヘンリー・フォンダがプロデューサーとなって映画化を実現。父親殺しの嫌疑をかけられた17歳の少年は有罪か?無罪か?陪審員を務めることになった12人の怒れる男たちによる白熱のトークバトルに観客は固唾を呑む。第7回(1957年)ベルリン国際映画祭を受賞した室内劇の傑作を魅力をご紹介。
- 室内劇・密室劇・会話劇がお好みの方
- ちょっと毛色の変わったサスペンスを楽しみたい方
- 議論や討論が好きな方、あるいは苦手意識を克服したい方
- 「言論の自由」について見識を深めたい方
『十二人の怒れる男』感想

96分間、リアルタイム・ディスカッション室内劇の傑作
12人の陪審員たちがひとつの部屋の中にいるだけである。なのに、これほどスリリングでエキサイティングな映画があるだろうか。登場人物たちは陪審員室からほとんど出ることなく(途中で化粧室に立つ程度)、容疑者少年の評議を進めていくのだが退屈な場面はまったくない。
うだるような猛暑のためシャツに汗ジミをこしらえる男たちの室内劇は、終始緊迫感をはらんでいる。パッツンパッツンに濃密な熱気で膨らんだ陪審員室は針で刺したら破裂しそうだ。
そんな12人の怒れる男たちの侃々諤々(かんかんがくがく)のトークバトルに立ち会ってしまったら最後、観客は手に汗握りながらラストの評決まで目が離せなくなるだろう。怒れる男たちのいる室内は、複雑極まる人間世界の縮図といえるかもしれない。
討論を通してあぶり出される人間の本性
12人の陪審員たちの個性はじつに粒立っている。考え方や価値観、バックグラウンドが違う12人が議論しあうことで、人間の本性、人間のもつあらゆる性質を引き出しあう。
怒り、欲望、愛情、葛藤、自己正当化、自己憐憫、嫉妬、屈託、屈曲、謀反気、迎合、逡巡、跳ねっ返り、ユーモア、利己心、変節、怠惰、偏見、短見、決めつけ、先入観、差別、気づかい、思慮深さ……これらが陪審員室内にあぶりだされる。
彼らはユニークな個性をぶつけあい、審議を深めていくことで、はからずも容疑の矛盾点を明らかにしていく。
当初、無罪を主張していたのは「陪審員8番」だけで残り11人は有罪票であった。ところがひとつひとつの矛盾が指摘されるごとに、ひとり、またひとりと有罪票から無罪票にひっくり返していく。あざやかに形勢逆転していくオセロゲームのように。『十二人の怒れる男』のもっともシビれるところだ。
12人の怒れる男たちが教えてくれる、アメリカ民主主義の原点
『十二人の怒れる男』を見て、あらためて感じ入ったのは民主主義の原理原則である。単純な多数決であれば、最初の予備投票の結果「1対11」で、有罪は確定していた。しかし、評決は、12人が全員一致でなければいけないというルール。
たったひとり、無罪票を投じた「陪審員8番」(ヘンリー・フォンダ)の意見に耳を傾けて、議論を継続していくところにアメリカ民主主義の「公正さ」があり、同時に「片付かなさ」がある。少なくともこの映画のなかで軍配を上げたのは「公正さ」の方だ。
21世紀、よりよき民主主義へのアップグレードは、喫緊の人類的課題だと思う。いまいちどデモクラシーの原点を見つめ直すうえで、『十二人の怒れる男』には見るべきものがある。私見では成文化された晦渋な文章を読むより、娯楽作品を通して確認したほうが腹落ち感が大きい。なにより眠くならないのがいい。
『十二人の怒れる男』キャストについて

「陪審員8番」(ヘンリー・フォンダ)
制作・プロデューサーでありながら主演もこなして辣腕ぶりを発揮している。テレビドラマだった『十二人の怒れる男』を映画化するにあたって、テレビでならしたシドニー・ルメットを起用したのが奏功したようだ。
フォンダとルメットによって選り抜かれた俳優たちは、舞台役者や新人も積極的に起用。ヘンリー・フォンダという人は、作り手としてもセンスがあることを今作で証明した。
演者としても申し分ない。会話劇を飽きさせることなく引っ張っていく、ヘンリー・フォンダの充実した演技は瞠目せしめるものがある。プロデューサーとして、そして12人の中心人物を演じる者として、陪審員室で繰り広げられるドラマの流れを誘導し、登場人物全員のパフォーマンスを最大限に引き出しているようだ。
ヘンリー・フォンダ演じる「陪審員8番」は善良な一般市民だが、徳の高い聖人君子という感じはしない。最初にたったひとり「無罪」を主張したのも、崇高な感情からというより、彼の心に兆した違和感やささやかな謀反気に端を発するような気がした。正直で誠実な人ではあるけれど、いささか凛としすぎるのだ。馴れ合いを排した近寄り難さは、個人的には好きなのだけれど。

「陪審員1番」(マーティン・バルサム)
陪審員長・進行役。ジュニアハイスクールでフットボールのコーチをしているだけあって恰幅がいい。少しでも納得がいかないことがあればそのまま放置せず、解決に向けて率先して動くタイプだ。映画が進行するにつれ、「陪審員1番」の両脇の汗ジミが大きくなっていくのだが、その汗ジミに真摯なものを感じた。けったいな印象だけれども。
「陪審員2番」(ジョン・フィードラー)
少し柔弱そうで、定見を持たないタイプのように見えるけれど、議論が進むにつれて旗幟を鮮明にしていく。この人がさりげなく見せる稚気がとてもユニークだ。
「陪審員3番」(リー・J・コッブ)
12人の中ではもっとも怒れる陪審員である。矯激な言動、怒りを破裂させるような演技から、舞台で培った役者の厚みを感じさせる。「陪審員3番」には息子がいるが、どうやら抜き差しならない確執があるようだ。愛憎相半ばする息子への噛み切れぬ思いが、17歳の少年容疑者を罰したい気持ちに駆り立てているのかもしれない。映画の最後、リー・J・コッブの演技には一見の価値がある。
「陪審員4番」(E・G・マーシャル)
「情」よりも「理」を重んじる株式仲買人を抑えた演技でこなしている。少年の有罪判決をつゆほども疑う様子はないが、動かしがたい証拠さえ提示すれば意見を変えるタイプである。偏見がなく、良くも悪くも論理に対して忠実なのだ。
「陪審員5番」(ジャック・クラグマン)
少年と同じ、スラム街出身の労働者を堅実に演じている。撮影当時、新人俳優だったこの人を抜擢したのがヘンリー・フォンダである。新人とは思えない落ち着いた屈託を表現できる俳優だ。
「陪審員6番」(エドワード・ビンズ)
実直で義理人情にあつい職人。年配者である「陪審員9番」に礼儀を欠いた態度をとった「陪審員3番」に、この人が釘を刺す場面は印象深い。
「陪審員7番」(ジャック・ウォーデン)
手っ取り早くすませてさっさと帰ろうぜ!というノリの人。この人のもっぱらの関心事は、少年の評決ではなくヤンキースの試合である。悪い人ではないけれど、面倒なことは嫌い、考えることは億劫、ややこしいことには関わりあいたくない━━ というタイプだ。
「陪審員9番」(ジョセフ・スィーニー)
12人の陪審員のなかでは最高齢。「陪審員8番」の次に無罪を主張する。紳士であり優しい心をもつ御仁だ。この人の透徹した人間洞察によって、証人のひとりである老人の目撃証言がにわかに怪しくなる。映画のエンディングで、「陪審員9番」の粋で洒落たふるまいが、深い余韻を残す。
「陪審員10番」(エド・ベグリー)
工場経営者。12人中、もっとも偏見の強い人間である。17歳の少年が貧困層であるという理由だけで、有罪と決めているふしがあり、根深い差別意識をうかがえる。目撃者たちの証言の信ぴょう性が揺らいでも、頑強に少年の有罪を主張するが、やがて陪審員の中で孤立していくさまが哀れだ。
「陪審員11番」(ジョージ・ヴォスコヴェック)
時計職人。最初は存在感が薄いが、審議が深まっていくうちに精彩を放つ人物。誠実を信条とする常識人であり、一度こうと決めたら絶対に譲らない反骨さを垣間見せる。
「陪審員12番」(ロバート・ウェッバー)
広告代理店勤務のサラリーマン。巧まざるユーモアの持ち主だが、”風見鶏” の傾向あり。けっして悪い人間ではない。良心もある。だが、自らの立場を明らかにし責任を負うことを極度に恐れてしまう人だ。「陪審員12番」のようなタイプが世間のマジョリティであり、彼らが社会経済活動をなめらかに動かしている。
『十二人の怒れる男』作品情報
| 監督 | シドニー・ルメット |
| 脚本 | レジナルド・ローズ |
| 撮影 | ボリス・カウフマン |
| 音楽 | ケニヨン・ホプキンス |
| 出演 | ・陪審員1番・・・マーティン・バルサム ・陪審員2番・・・ジョン・フィードラー ・陪審員3番・・・リー・J・コッブ ・陪審員4番・・・E・G・マーシャル ・陪審員5番・・・ジャック・クラグマン ・陪審員6番・・・エドワード・ビンズ ・陪審員7番・・・ジャック・ウォーデン ・陪審員8番・・・ヘンリー・フォンダ ・陪審員9番・・・ジョセフ・スィーニー ・陪審員10番・・・エド・ベグリー ・陪審員11番・・・ジョージ・ヴォスコヴェック ・陪審員12番・・・ロバート・ウェッバー |
| 上映時間 | 96分 |
| ジャンル | サスペンス |
あらすじ
舞台はニューヨークの法廷。実父の殺人容疑を掛けられた17歳の少年をめぐって、陪審員として選ばれた12人の男性たちが陪審員室で最終的な審議に入ろうとしていた。猛暑の午後、狭い陪審員室内で、陪審員たちは手っ取り早く評決をすませて帰宅したがっている様子。
少年は日頃から素行が悪く、目撃証言や状況証拠も揃っていため、有罪は明白かつ決定的であるかに見えた。しかし、冒頭の予備投票で11人が有罪票を投じたなか、たった1人無罪を主張する男がいた。「陪審員8番」(ヘンリー・フォンダ)である。もっとも彼は無罪を確信していたわけではない。少年の容疑に「合理的な疑い」が残っているため、十分話し合うことを希望しているのだ。
このまま評決が全員一致になると少年は尊属殺人で電気イス送りは免れない。そこで審議は再開。甲論乙駁していく12人の男たちの議論はエスカレートしながら証拠の矛盾点を明るみに出す。1対11だった最初の評決が覆されてゆく……
【コラム】歓迎すべきは「意見の不一致」
会議、ミーティング、家族との話し合い……意見がすんなりまとまると気持ちいいものですよね。いっぽうで、どれだけ話し合っても妥協点が見いだせず、わだかまりを残したまま話し合いを終えることもあるでしょう。
その場合、穏やかに「お互い妥協できないという点で一致しているね」と確認しあえたら御の字です。根気よく議論を重ねていけば、思ってもみない喜ばしい案が浮上することもなくはありません。
最悪なのは、話し合いが紛糾してニッチもサッチもいかなくなるケース。出口の見えない水掛け論になったり、感情むきだしで非難の応酬になったりすると、人間関係がギクシャクします。場合によってはシリアスな禍根を残すことにもなりかねません。
ここであなたに確認したいのは、「最初から意見が一致することは良いことなのか?」ということ。たしかに意見の一致はスカッとするものですが、よく考えてみると、最初から一致しているならわざわざ意見交換する必要はありません。議論や話し合いをするメンバーが複数人いても、すでに全会一致なら、何の進歩も成長もないということではないでしょうか。
会社のミーティングにせよ家族との話し合いにせよ、生産的な意義を見出し、お互いの利益と成長をもたらすうえで大切なことは、「意見の不一致」を歓迎する態度だと僕は考えています。相手との意見の不一致をおおらかに認め合うことは、自分がこれまで見えていなかった事実や知見や観照を教わるチャンスだからです。
『経営者の条件』という名著のなかで、ピーター・ドラッカーはこう述べています。
「意見の不一致が存在しないときには決定を行うべきではない」
対立意見がまったくないという状態は、参加メンバーが検討すべき議題について真剣に考えていない証左なのかもしれません。あるいは誰かに忖度したり、面倒な対立を避けたりしているのかもしれない。メンバーがそんな中途半端で及び腰の態度で重要な意思決定をしたらどうなるでしょう? 華々しい成果をあげるどころか、残念な結果をもたらすことにもなりかねません。
大切なのは、「意見の不一致」を歓迎する空気づくりです。
メンバーがお互いの意見を尊重しあいながら、意見を交換しあうなかで、お互いが見落としていたものに気付き、問題の打開策や秀抜なアイデアがその場で生まれる可能性は大いにあります。「意見の不一致」こそ、創造の母と申し上げてもいい。
今度、あなたが参加する会議やミーティングで「意見の不一致」が発生したら、『十二人の怒れる男』を思い出してください。11人が有罪票を投じるなかで、たった1人が無罪を主張したところから、劇的かつ感動のドラマが展開したことを思い起こしていただきたいのです。
「意見の不一致」があるからといって ”怒れる男(女)” になることはありません。むしろ不一致は慶賀すべきことであり、自分の小さな殻と狭い視野を打ち破る、好適な試金石と考えてみてはいかがでしょう。
『十二人の怒れる男』の動画を配信しているサービスは?
※ただし時期によっては『十二人の怒れる男』の配信およびレンタル期間が終了している可能性があります。